食と環境を考える京北スーパー
特集!ざ・けいほくオンライン
かつお節(本枯節)
鹿児島県枕崎市 株式会社マルモ

職人の熟練の技による手作業と自然の力で造り上げられる風味の良いかつお節
かつお節は古い時代からあったといわれ、神話「古事記」でも登場しています。
そして、かつお節はほとんど日本にしかなく、その生産量は、鹿児島県枕崎市で約40%、鹿児島県山川町で約30%、静岡県焼津市で約30%と、鹿児島県が全体の約70%を占め、日本一の生産量となっています。
この鹿児島県枕崎市にかつお節の製法が伝えられたのは1707年、約300年の歴史があり、今でも60軒のかつお節の製造業者が、かつお節を作っています。
そして、その60軒のかつお節の製造業者の中の1つである、株式会社マルモ様は、創業昭和3年、原料の仕入れから節の製造、削りまで一貫して行っています。


本枯節を削ったソフト削り(左)と荒節を削った花かつお(右)
原料のかつおは、かつおの群れが多いとされる赤道付近に、巻き網を仕掛けて獲ったかつおを、新鮮なうちに漁船の上で瞬間冷凍し、地元枕崎漁港で水揚げされたものを、枕崎の市場でせりにより仕入れます。
せりの会場では1kgから10 kgまでのかつおが、それぞれどのくらいの量があるかが黒板に記載され、それぞれの仕入れ業者に渡されたせり札に、どのかつおをどのくらい買うかを記入して、せり人が立っている黒板の上をめがけて投げ入れます。
かつお節の原料として適しているのは、脂肪分が多いと節にしたときにとっただしが脂で濁ってしまうことから、脂肪分が多すぎず、また少なすぎない適度な脂肪分をもったかつおを吟味して仕入れています。
仕入れたかつおは凍っているので1日自然解凍し、解凍後、生切り(なまぎり)という作業を行います。
これは、かつおの頭を落とし(頭切り)、腹部を切り取り(身おろし)、内臓を取り出したあと、身をかつおの背から腹にかけてタテに半分におろし、さらに、なるべく骨に包丁があたらないように薄く骨のまわりに付く身を骨に沿っておとしていき、半分になったかつおの身を背側の雄節と、腹側の雌節に切り分けます(合い断ち)。
生切りの作業は通常3本の包丁を使って行われ、数人の職人がかつおを半分にするところまでを行いますが、合い断ちについては、雄節と雌節の量を同じにするのが難しいということから、ここでは、職人の中でも親方しか切ってはいけないという決まりになっています。
この生切りの作業を1人の職人が1本の包丁で行う「薩摩切」という切り方がありますが、この切り方は昔に枕崎市に伝えられた切り方で、今ではできる職人はほとんどいないのですが、株式会社マルモ様の大茂会長は「薩摩切」ができる数少ない職人のお1人です。
生切り後は、雄節と雌節を血合いを下にしながら1本1本籠の中に並べていきます。
この作業を籠立て(かごだて)といいます。
ここで血合いを下にするのは、できあがったかつお節が曲がらないようにするためです。
そして、籠立てによりかつおが並べられた籠を10枚ずつ並べ、約90℃の煮汁が入った煮釜に入れて1時間半から2時間煮ます。
この作業は煮熟(しゃじゅく)と呼ばれ、かつおが腐ってしまうのを防ぎます。
煮釜にたまる煮汁は1週間から10日同じものを使用し、12時間ごとに煮沸をし、菌が繁殖するのを防ぎます。
この煮汁はかつおエキスとなるのですが、煮熟の段階で煮汁の味見をしてみると甘い味がしました。
煮熟したかつおは、手作業により1本1本身から骨を取り除きます。
この作業は骨抜き(ほねぬき)と呼ばれ、身に骨が残っていると、かつお節にした時に曲がってしまうために、慎重に行います。
また、この状態のものを「なまり節」といいます。
骨抜き後、なまり節は職人の手により、身が取れたところや、形が悪いものなど修正していきます。
修正後、再び籠に並べられたなまり節を燻製にします。
この作業は焙乾(ばいかん)と呼ばれ、ここでは3階建てで、それぞれの階に3部屋ずつある焙乾室の地下で、鹿児島県産のナラ、ブナ、カシなどの薪を職人の手により、炎がでないように燃やしながら煙りを出し、直火式で燻製にしています。
この作業は、各部屋ごと上下左右を入れ替え、また、1階から3階までを入れ替え、途中、籠からせいろに入れ替え燻製の状態を確認しながら熱したり、自然の力で冷ます作業を繰り返し、徐々に水分を抜いていきます。
取材のとき、実際に焙乾室を見学させていただきました。
地下には薪を燃やす部屋が3部屋あり、1つの部屋に、直径80㎝くらいの桶のような形をした入れ物に燃えている薪が入っていて、1部屋の中にその桶のようなものが20個くらい並べられていました。
そして、その部屋の中心には、補充用の薪が置いてあり職人がこの燃えている薪の間を通り、補充用の薪を足していきます。
暑さと煙で、非常に大変な作業だと感じました。
そして、1日に1部屋で2tもの薪を使用するそうです。
この焙乾作業によってできたものを荒節(あらぶし)と呼び、だしをとった時には燻製の香りが感じられ、主に関西方面で好まれています。
この荒節の表面を職人が削り、形を整えた裸節を再び籠の中に並べ、室(ムロ)と呼ばれる、カビ付けをする部屋に入れ、カビ付け作業を行います。
カビ付けをするために、カビの菌を裸節に吹き付ける製造業者もあるそうですが、ここでは自然と室の中についているカビ菌で、自然にカビ付けをしています。
株式会社マルモ様の大茂常務は、この自然に付いているカビ菌を「マルモ菌」と呼ばれていました。
1回目のカビ付けは室の中に入れて2週間から3週間で出てきます。
この時のカビを1番カビと呼び、その色は緑色をしています。
そして、室から出し、天日干しをし、1本1本表面のカビを払い落とします。
そして、再び室の中に入れ、2回目のカビ付けをします。
数日後、室の中から出し、天日干しとカビの払い落としを行い、室の中に戻し、3回目のカビ付けを行います。
そして、数日後、再び室の中から出し、天日干しをし、カビを払い落とす作業を行います。
このとき、最初青かったカビも茶褐色の優良カビとなります。
そして、職人が節と節とをたたいて音を聞き、水分が抜けたかを確認し、カビ付けと天日干しを繰り返し行いながら、約半年かけて本枯節に仕上げていきます。
こうしてできあがった荒節、本枯節は、鹿児島市にある削り工場に運ばれ、それぞれの用途にあわせた厚さに削り、パック詰めされ出荷されます。
鹿児島県はかつお節の生産量が日本一ということから、枕崎漁港のまわりには、たくさんのかつお節の製造業者がありました。
そして、かつお節として商品になるまでには、職人の熟練の技による手作業と自然の力で造り上げられているのだと感じました。
取材の際に、荒節でとっただしと本枯節でとっただしの味見をさせていただきました。
荒節は燻製の風味が強く、はっきりとした味でした。
本枯節はまろやかな風味でやさしい味でした。
どちらのだしも美味しく、かつおのだしの旨みがしっかりと感じられました。
職人の技による手作業と自然の力により造り上げられたかつお節の香りと風味をぜひご賞味ください。

本枯節(奥)と荒節(前)

大茂会長にお話をうかがいました
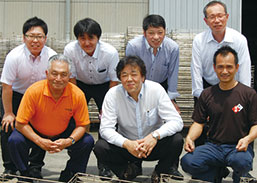
生産者の皆さんと取材班

枕崎漁港での水揚げ風景

大茂会長による「薩摩切」の実演

「薩摩切」はこの包丁一本で解体します

籠立て:血合いを下にして並べます

煮熟:90℃で1時間半から2時間水煮します

焙乾:鹿児島県産の薪で燻製します

カビ付け1回目:一番カビと呼ばれる緑色のカビ

天日干し:カビ付けと天日干しを何度も繰り返して仕上げていきます


