食と環境を考える京北スーパー
特集!ざ・けいほくオンライン
秋田県由利本荘市「まるごと売り込み連携協定」
雪の茅舎
本荘地域石脇地区 株式会社齋彌酒造店

秋田県由利本荘市の産品のご紹介。
由利本荘市の自然の恵みと、杜氏や蔵人たちのこだわりで造られた日本酒は、米の旨味、甘味が伝わってくる美味しい日本酒です。
KEIHOKUと秋田県由利本荘市は「まるごと売り込み連携協定」を締結しています。
鳥海山の恵みを受けた由利本荘市の地域産品について、掘り起しや売れる商品づくり、そして「由利本荘ブランド」の確立と、本物志向の品揃えをするKEIHOKUと、お互いより良い関係を築き発展させていこうということで一致し、平成27年5月14日に「まるごと売り込み連携協定」を締結いたしました。
今号では、地域産品の一部をご紹介いたします。

① 純米吟醸(精米歩合55%)720mL 1,500円+税
② 山廃純米(精米歩合65%)720mL 1,200円+税
③ 大吟醸(精米歩合45%)720mL 2,500円+税
④ 奥伝山廃本醸造(生貯蔵酒)(精米歩合65%)300mL 398円+税
※すべての商品の価格は2017年8月現在のものです。
本荘地域石脇地区にある株式会社齋彌酒造店様は、明治35年(1902年)に創業され、これまでに国内や海外の鑑評会で数多くの賞を受賞されている伝統ある酒蔵です。
創業から115年、今も当時のままの残されている酒蔵は国の登録有形文化財に登録されています。
酒蔵に入ってまず驚くことは、建物は昔のままなのに、酒蔵の中がきれいに磨かれ清掃されていることです。
酒蔵によっては雑菌の繁殖を防ぐためにホルマリンによる消毒を行う所もあるようですが、ここでは「酒蔵に住み着く菌のバランスを整える」「微生物の力で酒を造ってもらっているもの。
微生物の醸しやすい環境を作る」という発想で消毒はせず、毎日、蔵人が拭いたり掃いたりして、酒蔵の中をきれいにしています。
酒造りの原料となる米は、県内の契約農家または杜氏をはじめとする蔵人が自ら栽培したものを酒米使用しています。
そして、製造する酒の種類に合わせた精米歩合に削ります。
精米歩合は大吟醸酒は50%以下、吟醸酒は60%以下と決められていて、精米歩合の数値が低いほど米の中心部の〝しんぱく〟を残し、周りのタンパク質を削るため、より雑味がなくおいしい酒に仕上がります。
精米した米は洗米後、米の色の変化を見ながら浸漬をし、一晩寝かせ、翌日蒸し器で蒸します。
製造過程の中で使用される水は、由利本荘市の自然の恵みを受けた良質な「湧き水」を使用しています。
米のうまみを損なわずに、どこまで独自の個性的な酒が造れるか、水はとても重要な原料です。
蒸し後は米に麹菌を振りかけてから麹室に引き込み、蔵人の手により混ぜ合わせ麹菌を繁殖させ米麹を作ります。
この麹室は秋田杉で出来ていて、この秋田杉が室内の水分を吸収することにより乾いた環境を作り、この時米の中だけが湿っているので、麹菌が湿っている米の中に入っていくようにしています。
そして米麹は麹室の中で2日間かけて出来上がります。
蔵人は温度管理、湿度管理に注意して最良の米麹に仕上げます。
米麹が出来上がったら「酵母(酒母)」を育てます。
ここでは酵母の自家培養に取り組まれていて、長年に渡り選抜した酵母で独自の香味を生み出し、安定した酒質を醸しています。
そして、酵母(酒母)に米麹、蒸米、仕込み水を加え、低温長期発酵でじっくり発酵をします。
一般の酒蔵では「かい入れ」といって、発酵中にタンクの中をかき混ぜる作業をする所がありますが、ここでは、微生物の醸す世界に人間はできるだけ関与しないとの思いから、1度もかい入れをせず発酵させています。
かい入れをしないことから米が溶けていく姿が見て分かり、もろみの顔を見ながら蔵人により管理しています。
発酵が進むにつれ、米の抜け殻みたいなものが浮いてくるそうです。
そして、表面にできた膜みたいなものが透明になってきたら、あと1~2日で搾る合図だそうで、酵母たちも生き物で個性があり、仕込むタンクによって搾る日が前後する時もあるそうです。
こうして発酵中に溶けなかった麹や米を取り除き、新酒が誕生します。
一般の酒蔵では搾ったあとにろ過をし、割り水をする所もあるようですが、ここでは、ろ過や割り水をせず、搾られたままの醸された旨み成分がそのままで瓶詰めされます。
瓶詰め後は火入れを行います。
お燗のようにして火入れをする所もあるようですが、ここでは瓶の外から熱湯シャワーをかけて火入れをし、その後冷水シャワーで温度を下げて、それから冷蔵庫内に貯蔵して熟成させた後出荷をします。
由利本荘市の自然の恵みと、杜氏や蔵人たちのこだわりで造られた日本酒は、米の旨味、甘味が伝わってくる美味しい日本酒です。

明治35年(1902年)に創業され、今も当時の面影をとどめる株式会社齋彌酒造店様

自然の恵みを受けた良質な「湧き水」を使用します

蒸し米に麹菌を振りかけてから麹室に引き込みます

県内の契約農家と杜氏・蔵人が自ら栽培した酒米が原料です

秋田杉の麹室で蒸米に麹菌を混ぜ合わせます

お酒の醸造工程を詳しく教えていただきました

できあがったお酒を試飲するバイヤー
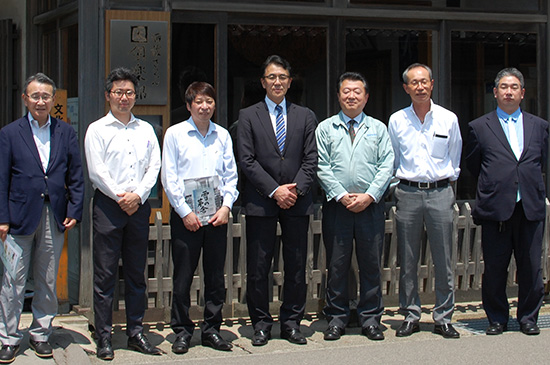
齋彌酒造店のみなさんと取材班


